 |
 フグ中毒ってどんな病気? フグ中毒ってどんな病気? |
 |
高い致死率 |
| |
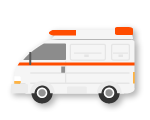 日本の動物性自然毒による食中毒の大部分は、フグ中毒によるものです。 日本の動物性自然毒による食中毒の大部分は、フグ中毒によるものです。
全食中毒の中でフグ中毒は、発生件数の約1%、患者数の約0.1%を占めるにすぎません。しかし、フグ中毒による死者は、全食中毒死者の約半数にもなります。 |
 |
減少しないフグ中毒患者 |
| |
1983年、当時の厚生省からフグ食用のガイドラインが出されました。
これにより、フグ中毒の発生件数は確実に減少しましたが、最近10年間では毎年25件前後発生しています。患者数は約40人で、死者数は数人程度で横ばい状態です。 |
|
 フグ中毒の症状は? フグ中毒の症状は? |
 |
食後20分ごろから |
| |
 フグ中毒の症状は、通常では食後20分〜3時間であらわれます。特に、飲酒時には症状が早くあらわれます。 フグ中毒の症状は、通常では食後20分〜3時間であらわれます。特に、飲酒時には症状が早くあらわれます。
唇、舌先のしびれから始まり、指先のしびれがあらわれます。頭痛、腹痛、腕痛をともなうこともあります。
つづいて、歩行困難、嘔吐、言語障害、呼吸困難、血圧低下が起こり、最後には呼吸麻痺によって死亡してしまいます。
致死時間は、4時間〜6時間がもっとも多く、長くても8時間程度です。 |
|
 フグ中毒の治療法は? フグ中毒の治療法は? |
 |
応急処置程度 |
| |
 現在では、解毒剤などは存在せず、食べたものを吐き出させるといったような、応急処置しか治療法がありません。 現在では、解毒剤などは存在せず、食べたものを吐き出させるといったような、応急処置しか治療法がありません。
 胃腸内の毒素の排除 胃腸内の毒素の排除
 流血中の毒素の排除 流血中の毒素の排除
 人工呼吸を長く続ける 人工呼吸を長く続ける
 輸血は避け、強心剤の投与を行う 輸血は避け、強心剤の投与を行う |
|
 フグ中毒の原因は? フグ中毒の原因は? |
 |
フグ科の魚類 |
| |
 フグ目の魚類には、フグ科 フグ目の魚類には、フグ科 、ウチワフグ科、ハリセンボン科 、ウチワフグ科、ハリセンボン科 、ハコフグ科などがあります。 、ハコフグ科などがあります。
フグ毒を持つものは、フグ目の中でもフグ科だけに限られています。有毒のものは、50種前後とされています。一般的に知られているのは、クサフグ、コモンフグ、ヒガンフグ、ショウサイフグ、マフグ、メフグなどがあります。また、マンボウ、ハリセンボンもテトロドトキシンを持っているといわれています。 |
 |
さまざまなフグ毒 |
| |
フグの毒性は、種類や組織によって大きく異なっています。さらに、有毒フグであっても、その毒性には著しい個体差、季節差、地域差がみられます。
一般的には、卵巣と肝臓の毒性が強く、筋肉は無毒の種類が多いです。産卵直前がもっとも毒性が高いといわれています。一部、ドクサバフグのように筋肉の毒性も高いものや、サバフグやカワフグのようにすべての組織で無毒のものもいます。 |
|
 フグ中毒の成分は? フグ中毒の成分は? |
 |
テトロドトキシン |
| |
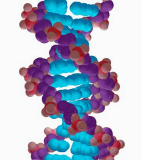 フグ毒の成分は、テトロドトキシン(TTX)で、強力な神経毒です。毒性はシアン化ナドリウムの1000倍といわれています。 フグ毒の成分は、テトロドトキシン(TTX)で、強力な神経毒です。毒性はシアン化ナドリウムの1000倍といわれています。
神経や骨格筋の細胞膜には、興奮の伝達に関与するナトリウムイオンのみを通過させる蛋白質でできているチャンネル(ナトリウムチャンネル)があります。テトロドトキシン(TTX)は、ナトリウムチャンネルに特異的に結合して、細胞外から細胞内へのナトリウムイオンの流入を阻止し、結果として興奮伝達を停止させてしまいます。
毒性は、マウスに対するLD50値は1kg中322μg、ネコで1kg中0.2mg、ヒトで1kg中2mgです。
 家庭の医学:シアン中毒 家庭の医学:シアン中毒 |
 |
フグ以外のテトロドトキシン |
| |
テトロドトキシン(TTX)はもともと動物の生体防御物質で、自然界に広く分布しています。
フグ以外でも、両生類のカリフォルニアイモリ、アテロパス属のカエル、魚類のツムギハゼ、節足動物のオウギガニ類、軟体動物のヒョウモンダコ、ボウシュウボラ、バイ など、多種多様な生物に存在していることが確認されています。 など、多種多様な生物に存在していることが確認されています。
ボウシュウボラ、バイでは、テトロドトキシン(TTX)中毒が起きた例も報告されています。 |
|
|
|
 |
