実相寺のすぐ近くにある延寿寺。
互いの距離は徒歩2分~3分程度の距離しかありません。かつて幕府が置かれていた東京や鎌倉ならいざ知らず、三浦市でこんなにも近くに二つの寺院が並んでいるなんて珍しいですよね。漁師町として多くの人が住んでいた場所なのかもしれません。
アクセスは最寄りのバス停は京急バスで宮田になります。徒歩10分くらいかな、だけど周囲に景色の変化が少ないので体感ではかなり長く感じます。境内から少し離れた場所に広い駐車場があります。
周辺では開発が行われる予定で埋め立てや土地買収が行われたまま放置されてしまった場所が荒れ地となっています。

由緒
手持ちの資料より
別名を寿福大黒天といいます。
日蓮宗のお寺で、山号は寿福山、寺号は延寿寺といいます。本尊は釈迦如来像です。開基は日範で1310年(延慶3年)になります。1284年(弘安7年)に建立されたという資料もあります。
日範は鎌倉市大町にある上行寺の開山と同一人物のようです。日蓮が後継者と定めた弟子たちの六老僧(日昭、日朗、日興、日向、日頂、日持)には入りませんが、九老僧の一人に数えられた僧侶です。当時としてはとても珍しく100歳を超える長寿を全うした人物です。
三浦七福神の大黒天が祀られています。江戸時代の文化年間(1804年~1817年)、日龍上人が彫ったと伝えられています。俵の上で打ち出の小槌を持ち、袋を背負っています。五穀豊穣の神様と言われています。鎌倉市扇ガ谷にある薬王寺にも日龍上人が彫ったと伝えられる大黒天像があります。
また、三浦市の文化財に指定されている鰐口があります。
案内看板より
三浦七福神 寿福大黒天(延寿寺)
ここ寿福山延寿寺は、日蓮聖人門弟第九老僧の一人、大善阿闍梨日範上人の開基で、1310年(延慶3年)3月に建立されました。
日範上人は百二十余歳の長寿を保たれて、元応2年7月22日、眠るがごとき大往生を遂げられました。現在は惜しくも枯れてはおりますが、上人お手植えの松が境内に保存されております。
山号の寿福山延寿寺は、上人の長命を寿ぎまして名付けられました。本尊釈尊、日蓮上人自作の開運鬼子母尊神を祀り、立正安国法華経弘通の道場として七百有余年続く名刹です。
当寺の寿福大黒天は、日範上人の門弟日龍上人が一刀三礼の儀をもってお刻みになったもので、甲子の日が御縁日で、富貴、長寿、特に豊かな食生活が約束されるという、まことにめでたい大黒天です。
平成6年1月 三浦市
写真
延寿寺の写真

入り口(2019年6月19日撮影)
すぐ近くにある実相寺と同じ日蓮宗のお寺です。
合併しちゃえばいいのにと思った人もいるかもしれませんが、それぞれ別々の寺院として存在しています。
写真を撮影しているときには気付かなかったのですが、お題目が刻まれた石塔に自分の影が映り込んでしまいました(^^;)

参道(2019年6月19日撮影)
訪れるたびに、どこか神社っぽいお寺だなって感じる造りになっています。
観光地でもないし、周辺には住宅も少ないので、普段は訪れる人は少ないです。たまに七福神巡りのイベントが実施されたりもするので、その時は訪れる人が多くなるようです。記念の朱印を書いてもらう人が多くなります。

境内(2019年6月19日撮影)
延寿寺の境内です。交通安全祈願の幟が奉納されています。
正面に見えるのが本堂、左に見えるのが日範上人お手植えの松です。遠くから見ると釣り鐘が掛けられている鐘楼みたいですよね。

本堂(2019年6月19日撮影)
木造の本堂ではなくコンクリート造の近代的な本堂です。昭和時代に建てられたものだと思います。

堂内(2019年6月19日撮影)
ちょこっとだけ堂内を覗いてみました。
どこでもそうなんですが、扉を開ければ堂内に入ることができます。私は信仰のために訪れているわけじゃなくて写真を撮ったり観光のために訪れているので、堂内に入ることはほとんどないけど。
三浦七福神のお寺のためでしょうか、他の寺院に比べるとウェルカムな雰囲気があります。

日範上人お手植えの松(2019年6月19日撮影)
日範上人お手植えの松になります。でも、枯れちゃったようです。
もし本当だとすると樹齢700年くらいになるのかな。実際にはそこまでの樹齢かどうかは疑問だけどね。それでもかなり古いものになると思います。真偽のほどはわかりませんが、枯れていなかったらとても立派なマツだったと思います。この松の木を見ることが目的で訪れる人もいるかもしれないですね。
海に近い場所だし、気候の関係も考えるとクロマツかなーって思います。

日範上人お手植えの松(2019年6月19日撮影)
日範上人お手植えの松の根本が日範上人の廟所にもなっているようです。
日範は100歳以上まで生きた長寿の僧侶です。当時としてはバケモノなんじゃないかと思われる程の長寿です。もし今の時代に生きていたら間違いなく200歳オーバーですね。

井桁に橘紋(2019年6月19日撮影)
とてもかわいい家紋だと思いませんか?
日蓮宗のシンボルマークの家紋です。日蓮の家紋が井桁に橘紋だったためです。
日蓮の先祖は橘氏に由来するため橘紋を使っていたそうです。数年前の大河ドラマ「おんな城主直虎」の井伊家も同じ系統に由来するらしいです。
植物の写真

アジサイ(2019年6月19日撮影)
写真撮影を楽しみながら、史跡巡りも楽しみ、ブログ作成も楽しむみたいな感じでやっています。
そんなわけでいつも新しいデジカメが欲しいなーと思っています。スマホでもいいんだけど、やっぱりデジカメの方が綺麗に撮れるんですよー。一眼レフはいらないけれど、高級なコンパクトデジカメが欲しいです。
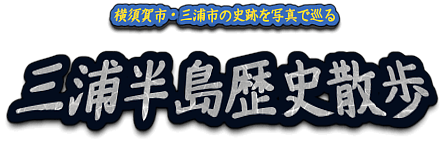


コメント