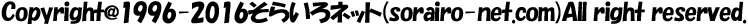| 「はぁ、はぁ、はぁ。やっと着いた。」
集会場は村の真ん中にある。いつ、誰が作ったのかわからないが、太い三本の柱によってやぐらが組まれていた。僕が生まれた時から、この光景はまったく変わらない。家からそれほど遠くないところにある集会場だが、思いのほか遠く感じた。まだ、全員集まっていないようである。
「遅いじゃない、なにやってたの。」
人ごみの中から話し掛けてきたのは、やっぱりミナミだった。
「え? うん、ズボン履き替えてたから。」
「これが? 」
「う、うん・・・」
僕のズボンには興味がないのか、突然の集会のことを話し出した。
「ほら、あの真ん中にいる人。昼間来た、王国の兵隊さんみたいよ。」
「兵隊さん?」
気にもとめていなかったが、たしかによく見ると、やぐらの上にはムラオサと王国の制服を着ている男が立っている。王国の者が、こんな村になんの用があってやってきたんだろうと聞こうとする間もなく、ミナミがいった。
「一体、なにしにきたのかしら?」
「し、知るもんか。そんなこと僕に聞かれたって。」
自分の言葉をさえぎるように話し掛けられたため、少し不愉快そうにそういった。しかし、なにをしに来たのかはだいだい見当がついていた。何年かに一度、王国にこの村の若者を兵に出さなければならないのである。その時がきたのだと、みなわかっていた・・・
村人全員が集会場に集まり、ムラオサがおもむろに口を開いた。
「えー、では、集会を始める。今日集まってもらったのはいうまでもなく、こちら、王国からの使者が来ていただいたからである。この村にも王国に貢献できる日がやってきた。この村から若者の男子一名を王国の兵士として送り出すことになったのだ。」
思っていたとおり、アカガミだった。昔は、夜中に王国から使者がやってきて、国王の印の押された赤い紙を家の玄関のドアに貼り付けていった。だから僕らの村では徴兵のことを、アカガミと呼んで忌み嫌われていた。今では、王国との話し合いにより、ムラオサが兵士になる者を決めることになっている。
ムラオサの話の最中、僕を見つめる視線に気が付いた。視線の方向に目を向けると、ガイアがにらめつけるような目でこちらを見つめていた。おそらく自分が行きたいと思っているのであろう。本心なのかどうか定かではないが、日頃から、この村を出て行きたいといっていた。僕はもめごとを嫌って、目線をそらした。
王国の兵士といっても、僕にはあまり関係のないことだった。村で畑を持つこともできないような僕が、兵士として選ばれるはずもないと思っていた。僕にはもっと違った生き方がある、そう思っていた。
最後にムラオサはこういって集会を締めくくった。
「王国の兵士になることはとても名誉なことである。明日、名誉なる者には、私が直々に伝えることにする。」
「ねえ、ちーず。兵隊に行かなくちゃいけないのって誰になるのかしら?」
ミナミが話し掛けてきた。
「うーん、たぶん、ガイアが行くことになるんじゃないかな。自分で行きたいっていってたし。マッシュだって、オルテガだっているんだ。僕には関係ないよ。」
「でも、もしもってことがあるじゃない?もしも、わたし・・・」
わざとらしく自分を指差し、
「ワタシが選ばれるってこと? 」
「ち、違うわよ! ちーずが選ばれるってこと。」
といって、僕がボケたのをわかっていながら突っ込んでくる。
「え? だって、僕が選ばれるなんてことは絶対にありえないよ。僕のような弱い人間が兵隊として王国に行ったら、それこそ僕らの村にとっては恥だよ。そんなこと、あのムラオサがするはずないよ。」
「そ、そういわれてみれば、そうね。うん、少し安心しちゃった。」
納得したふうのミナミの笑顔を見て「失敬だなー」といって二人で笑っていた。 |