 |
 一酸化炭素中毒の概要は? 一酸化炭素中毒の概要は? |
 |
おもな症状 |
| |
 頭痛 頭痛
 深昏睡(しんこんすい)など中枢神経系の障害 深昏睡(しんこんすい)など中枢神経系の障害 |
 |
起こりやすい合併症 |
| |
 肺水腫(はいすいしゅ) 肺水腫(はいすいしゅ)
 腎障害 腎障害 |
|
 一酸化炭素中毒ってどんな病気? 一酸化炭素中毒ってどんな病気? |
 |
一酸化炭素がヘモグロビンと結合 |
| |
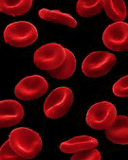 一酸化炭素(CO)は、血液中のヘモグロビン(Hb)との親和性が極めて高く、酸素(O2)の200倍以上の親和性を持ちます。その親和力で一酸化炭素とヘモグロビンが統合し、一酸化炭素ヘモグロビン(CO-Hb)を形成します。 一酸化炭素(CO)は、血液中のヘモグロビン(Hb)との親和性が極めて高く、酸素(O2)の200倍以上の親和性を持ちます。その親和力で一酸化炭素とヘモグロビンが統合し、一酸化炭素ヘモグロビン(CO-Hb)を形成します。
このため、血液中に一酸化炭素ヘモグロビンが大量に生成され、ヘモグロビンは酸素を運搬することができなくなってしまいます。同時に一酸化炭素は細胞のミトコンドリアの機能も障害します。
さらに、一酸化炭素ヘモグロビンは、単に酸素を運搬しないというだけではなく、残ったヘモグロビンの酸素親和性を増し、同量のヘモグロビンを失った貧血よりも組織への酸素供給が著しく減少します。 |
 |
全身の低酸素症 |
| |
一酸化炭素中毒は、全身の低酸素症で、まず酸素需要の多い脳に障害があらわれます。
より早く治療を行えば、救出時に意識が障害されていても、完治することが可能です。しかし、処置が遅れると重大な障害が残り、その後も回復する可能性はありません。 |
|
 一酸化炭素中毒の原因は? 一酸化炭素中毒の原因は? |
 |
不完全燃焼 |
| |
 一酸化炭素中毒は、石油の不完全燃焼、火災、自殺のための自動車の排気ガスの引き込みなどで発生します。炭鉱事故などでも発生します。 一酸化炭素中毒は、石油の不完全燃焼、火災、自殺のための自動車の排気ガスの引き込みなどで発生します。炭鉱事故などでも発生します。
都市ガスが、石炭ガスから一酸化炭素をほとんど含まない天然ガスに切り替えられ一酸化炭素中毒の患者さんは減少しましたが、現在でも全中毒死亡者数の過半数をしめています。
最近ではガス給湯器の誤った使い方による一酸化炭素中毒の発生があります。 |
|
 一酸化炭素中毒の症状は? 一酸化炭素中毒の症状は? |
 |
頭痛や吐き気 |
| |
 血液中の一酸化炭素ヘモグロビンの量が増加するにつれて重症化します。頭痛、疲れやすい、判断力の低下、吐き気・嘔吐、意識障害、痙攣(けいれん)があらわれます。 血液中の一酸化炭素ヘモグロビンの量が増加するにつれて重症化します。頭痛、疲れやすい、判断力の低下、吐き気・嘔吐、意識障害、痙攣(けいれん)があらわれます。
血管の透過性が亢進し、肺水腫(はいすいしゅ)、脳浮腫(のうふしゅ)を起こすケースもよくみられます。
頭部CTで、淡蒼球(たんそうきゅう)という部位に低吸収像が認められる場合は、予後は不良です。 |
 |
CO-Hbの濃度と症状 |
| |
| CO-Hb濃度 |
症状 |
| 0〜10 |
なし |
| 10〜20 |
鮮紅色の皮膚、頭痛 |
| 20〜30 |
拍動性頭痛 |
| 30〜40 |
全身倦怠感、嘔吐、視力障害 |
| 40〜50 |
頻脈、呼吸促迫 |
| 50〜60 |
昏睡、痙攣、無呼吸をともなうことも |
| 60〜70 |
弱い呼吸、ときに死亡 |
| 70以上 |
呼吸停止し死亡 |
|
 |
間欠型一酸化炭素中毒 |
| |
発症メカニズムは不明ですが、一度回復してから、再び昏睡(こんすい)に陥る間欠型一酸化炭素中毒もあります。 |
|
 一酸化炭素中毒の治療法は? 一酸化炭素中毒の治療法は? |
 |
酸素補給 |
| |
 高圧酸素療法、もしくは純酸素による機械呼吸が、一酸化炭素のすみやかな排泄と、低酸素に陥っている組織への酸素供給を兼ねた効果的な治療法として行われています。 高圧酸素療法、もしくは純酸素による機械呼吸が、一酸化炭素のすみやかな排泄と、低酸素に陥っている組織への酸素供給を兼ねた効果的な治療法として行われています。 |
 |
軽症例では安静に |
| |
意識障害をともなわない軽症の場合は、新鮮な空気のもとで自発呼吸を十分に行えば、自然治癒します。 |
|
 一酸化炭素中毒かなと思ったら? 一酸化炭素中毒かなと思ったら? |
 |
安全な場所へ移動を |
| |
まず何よりも、新鮮な空気の流れている場所に移動します。
意識が障害されている場合は、下顎を上げて気道を確保した上で、急いで医療機関へ受診してください。 |
|
 一酸化炭素中毒の応急処置は? 一酸化炭素中毒の応急処置は? |
 |
酸欠と一酸化炭素中毒 |
| |
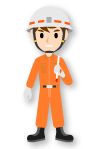 ガス中毒といえば、一酸化炭素中毒の代名詞のように使われていますが、現在の都市ガスに一酸化炭素は含まれておりません。最近の都市ガス中毒は、酸欠と考えられています。密閉した部屋で火を使用したため、空気中の酸素が不足したことが原因となります。 ガス中毒といえば、一酸化炭素中毒の代名詞のように使われていますが、現在の都市ガスに一酸化炭素は含まれておりません。最近の都市ガス中毒は、酸欠と考えられています。密閉した部屋で火を使用したため、空気中の酸素が不足したことが原因となります。
石油ストーブ、炭、練炭などの不完全燃焼、自動車の排気ガスによる自殺では一酸化炭素中毒がみられます。 |
 |
二次災害に注意して |
| |
もし液化石油ガス(LPG)の場合は、引火爆発による二次災害に注意しましょう。
まず、中毒を起こした人を新鮮な空気のところに運びます。意識がなく嘔吐している場合は、側臥位(そくがい)または昏睡体位(こんすいたいい)をとらせ、気道への誤嚥(ごえん)を防止します。呼吸がない場合は、ただちに心肺蘇生法を開始しなければなりません。
治癒しても、1週間〜2週間後、再び意識障害や見当識障害などが出ることがあるので、軽症でも医療機関の受診を受けましょう。 |
|
|
|
 |
