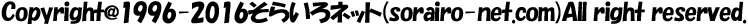|
必ず治療を受けましょう |
| |
 急性白血病と診断された後、治療しないで放置しておくと、数日〜数週間で死亡してしまいます。 急性白血病と診断された後、治療しないで放置しておくと、数日〜数週間で死亡してしまいます。
診断が確定したら、すぐに入院し、治療を開始する必要があります。 |
| |
 |
寛解導入療法(かんかいどうにゅうりょうほう) |
| |
|
 |
抗がん薬による治療 |
| |
|
|
治療にはまず、数種類の抗がん薬を組み合わせて投与する、併用化学療法を行います。
これを寛解導入療法と呼びます。 |
| |
|
 |
白血病細胞を減少させる |
| |
|
|
寛解導入療法の目的は、骨髄中にあふれる白血病細胞を100分の1〜1000分の1以下に減少させ、骨髄にスペースを作らせ、正常な血液を造る能力を回復させることにあります。
白血病細胞が顕微鏡では見付けられない100分の1以下になり、血球数が正常化する状態を完全寛解(CR)と呼びます。
「治癒」という言葉を使わないのは、見付けることができなくても、体内のどこかには白血病細胞が潜んでいる状態のためです。 |
| |
|
 |
骨髄性白血病とリンパ性白血病の治療の違い |
| |
|
|
急性骨髄性白血病と、急性リンパ性白血病とでは、寛解導入療法に使用する抗がん薬が異なります。
急性骨髄性白血病の場合は、イダルビシン、またはダウノルビシンとシダラビンの併用化学療法を行います。急性リンパ性白血病の場合は、エンドキサン、ダウノルビシン(またはドキソルビシン)、ビンクリスチン、プレドニゾロン、シクロホスファミド、L-アスパラギナーゼの併用化学療法が一般的です。
急性骨髄性白血病では65%〜80%、急性リンパ性白血病では70%〜90%で、完全寛解が得られます。 |
| |
|
 |
抗がん薬治療による副作用 |
| |
|
|
化学療法は、白血病細胞を殺すのみならず、正常な血液細胞も障害してしまうので、抗がん薬投与後は、一時的に血液が造られない状態になってしまいます。
赤血球、血小板は輸血で補うことができますが、白血球は輸血することができません。
白血球の減少にともなって、細胞、カビなどの真菌(しんきん)による感染症のリスクが高まります。抗生剤、抗真菌薬を投与して、予防と治療を行います。
白血球を増やす顆粒球コロニー刺激因子(G-CSF)という薬剤がありますが、顆粒球コロニー刺激因子(G-CSF)が白血病細胞を増やす可能性が低いと判断された場合のみに使用できます。
吐き気、嘔吐、脱毛、口内炎 、下痢などの副作用も認められます。 、下痢などの副作用も認められます。 |
| |
 |
寛解後療法(かんかいごりょうほう) |
| |
|
 |
寛解後も治療を継続 |
| |
|
|
完全寛解したといっても、治療を中止してしまうと、体内に残っている白血球細胞が再び増殖を開始し、白血病が再発してしまいます。
完全寛解が達成されたあとも、治療を継続し、体内に残っている白血病細胞をゼロにするように治療を続けます。これを寛解後療法と呼びます。
急性リンパ性白血病では、中枢神経に白血病細胞が残っていることが多いので、中枢神経を包んでいる髄液の中に、直接抗がん薬を投与することがあります。 |
| |
|
 |
化学療法と造血幹細胞移植 |
| |
|
|
 寛解後療法には、化学療法を1年〜2年続ける治療法と、化学療法に続いて造血幹細胞移植を行う治療法とがあります。 寛解後療法には、化学療法を1年〜2年続ける治療法と、化学療法に続いて造血幹細胞移植を行う治療法とがあります。
どちらを選択するかは、白血病細胞の染色体異常、年齢、完全寛解達成までの時間など、さまざまな因子を総合的に評価して決定します。再発の可能性が高い患者さんには造血幹細胞移植を、再発の可能性が低い患者さんには化学療法を継続するのが一般的です。 |
| |
|
 |
微小残存病変(MRD) |
| |
|
|
再発の可能性が予測できない予後中間群の患者さんに関しては、治療法を選択する指標がありません。さらに予後因子は、必ずしも絶対的なものではありません。
そこで最近注目を集めているのが、完全寛解に入った後、水面下の白血病細胞の量を、白血病の遺伝子異常などを利用して明らかにするMRD(微小残存病変)を用いて、その推移をみて治療法を決定する試みも行われています。 |